参考資料:なし
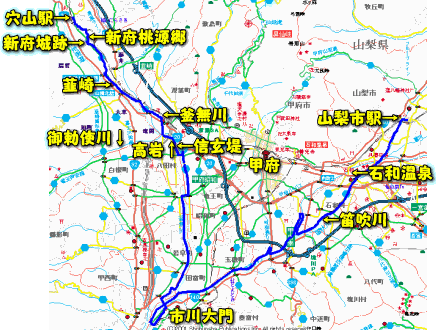
今シーズンは既に梅と桜を撮影したので、今度は桃の撮影に行くことにした。
中央線の韮崎の先にある穴山駅まで輪行。
今日は快晴だが、甲府盆地は例によって霞んでおり、
八ヶ岳と富士山はほとんど見えなかったが、
南アルプスの鳳凰三山は何とか見えた(今日の撮影はこれが見えないと話にならない)。
10分ほど走ると新府桃源郷の桃畑が広がり、菜の花もちらほら咲いている。
新府共選場(桃の選別をする場所か?)では花見会が行われていた。
なお、新府桃源郷の開花情報はここの「旬の花だより」を参照した。またここにコース案内がある。
少し進むと、武田勝頼の(滅亡前の)最後の居城だった新府(しんぷ)城跡に到達する。
249段の急な階段を登ると頂上に出る。
ここでも祭りをやっていて出店がずらりと並び、
三波春夫の歌声(地元のご当地音頭?)がスピーカーから流れていた。
新府(しんぷ)城の詳細はここやここを参照されたい。
続いて県道17号線を南下し、釜無(かまなし)川と御勅使川(みだいがわ)の合流地点に向かう。
ここで御勅使川の治水の歴史を簡単に説明する。
釜無川へ流れ込む御勅使川は普段は水量が少ないが、
大雨が降ると氾濫し、下図の「旧河道」に示すように甲府盆地に洪水をもたらした。
そこで武田信玄は治水を行い、まず川の流路を下図の点線のように変え、
釜無川との合流点付近で流れを高岩に当てて水勢を弱め、
その下流に信玄堤を設けて氾濫を防いだ。
この治水に伴い、御勅使川の上流の扇状地では、石積出し、将棋頭(しょうぎがしら)といった
流路を変えたり分岐させるための工夫がなされた。
御勅使川の治水の歴史に関しては、ここ、ここ、ここなどに解説がある。
また山梨日日新聞社の「グラフ信玄堤」、「信玄堤」に詳しい説明が書かれている。
御勅使川と釜無川の合流地点を撮影した後、高岩、信玄堤を撮影する。
信玄堤には、信玄の治水で使われた聖牛(せいぎゅう)の複製がずらりと並んでいた。、
これは洪水時に河岸に当る水をはね、河川の安全をはかるのを目的とした木製の構造物で、
こことここに説明されているが、これが本当に効果があるものなのか理解できなかった。
ここからは釜無川沿いのサイクリングロード(以下CRと略記)を走る。
なお、甲府盆地のCRについてはここを参照されたい。
このCRは自転車も人もほとんど通らない。
甲府盆地の南端の市川大門に近づくにつれ、向かい風が次第に強くなってきた。
釜無川と笛吹川の合流点の手前の富士川大橋でUターンし、今度は笛吹川沿いのCRを走る。
ここからは追い風に変わる。
実は最近睡眠不足で、今朝も始発で来たため、次第に睡魔が襲ってきた。
また、電車内で寝たり起きたりを繰り返したせいか、頭痛がしてきた。
このように体調不良のため、追い風ながら走るのが苦痛で、途中で何度も休憩した。
このコースは4年位前にbromptonで走ったことがあるが、
そのときこのあたりで、前方にCRをまたいで人が倒れているのを発見したことを思い出した。
死体だと思ったので(>_<)、やっかいなものを目撃したと思いながら恐る恐る近づくと、
人はむっくり起き上がってスタスタ立ち去った。
単にCR上で昼寝をしていただけだったらしい。
いくら通行量がほぼゼロだと言っても、道の上で昼寝をするとは全く人騒がせだ。
ようやく山梨市に到着し、走り輪行して帰宅。
なお、今まで日焼け止め(強力なタイプ)を顔にしか塗らなかったが、
腕や足が真っ赤になるとジムでかっこ悪いので、今回は腕と足にも塗り、効果を調べた。
その結果、今日は一日中晴天だったが、全然日に焼けず、効果は抜群であることが分かった。
腕と足には表だけ塗ったが、腕の表と裏の間に、日が当たるのに塗りそこなった隙間が少しあったため、
その細長い部分だけが赤くなってしまった(^^;)。
| 穴山駅付近から南アルプスの鳳凰三山の眺望。 ここで一曲(←音が出ます。) |
|
| のどかな風景の中を走る。 | |
| スモモ?を入れて撮影。 | |
| 次第に桃畑が広がる。 | |
| 菜の花も咲いている。 |
| 霞んでいる茅ヶ岳(かやがだけ)。 | |
| 新府共選場では花見会が行われていた。 | |
| 桃と菜の花を入れて撮影。 | |
| 向こうに見える小山が新府城跡。 | |
| 再び菜の花を入れて撮影。 | |
| 桃のピークはやや過ぎていたようだ。 | |
| ここによると、これは鑑賞用の「はなもも」らしい。 | |
| 南アルプスを入れて撮影。 | |
| 新府城跡に向かう。 | |
新府城跡。 右は昔の想定復元図。 上の写真は、右の図の右側。 |
| 結構急な249段の階段を登ると頂上に着く。 | |
| 祭りをやっていて、これからお御輿が出発するらしい。 | |
| ロボット君登場。 | |
| 城跡から北側の眺望。 八ヶ岳は霞んでいてほとんど見えない。 |
|
| 西側の眺望。 眼下に釜無川が流れている。 |
| 韮崎市内のなめこ壁の土蔵?。 | |
| 御勅使川(みだいがわ)との合流点付近の釜無川。 | |
| 写真で上から下に流れる御勅使川(みだいがわ)が、 右から左に流れる釜無川に注ぐ。 |
|
| 合流後、流れを向こう岸の壁(高岩)に当てて、 水のエネルギーを減らす。 |
| 中央左が高岩、中央右が信玄堤。 (手前が下流)。 |
|
| 観光用?の木製の聖牛(せいぎゅう)。 | |
| 信玄堤と、ずらりと並んだ聖牛。 | |
| 現代の聖牛はコンクリート製。 | |
| 草がからまっている。 | |
| これも現代の聖牛か? | |
| サイクリングロード沿いにずらりと並ぶ。 | |
| 開国橋付近の釜無川。 | |
| 釜無川CR。 | |
| 富士山は霞んでいてほとんど見えない。 |
笛吹川。 |
富士川大橋付近の中州から下流の眺望。 左が笛吹川。右は釜無川。 この先800m位のところで合流し、 富士川となる。 |
釜無川。 |
| ここからは笛吹川沿いを走る。 CR沿いなのに「シートベルトをつけましょう」の看板が |
|
| 堤防の上は一般道で、下をCRが通っている。 左は笛吹川。 |
|
| 笛吹川沿いは草地が多い。 | |
| 同上。 ここで一曲(←音が出ます。) |
| 石和温泉付近の笛吹川。 桃の花祭りの最中で、ノボリがずらりと並んでいた。 |
|
| これは観光用?の聖牛。 | |
| これは木材合掌枠と呼ぶらしい。 | |
| このとき(奇しくも1年前の同じ日)行った京戸川扇状地の遠望。 甲府盆地の縁にはいくつもの扇状地が並んでいる。 |
|
| 山梨市付近の笛吹川。 |
次のレポートへ ツーリングの記録へ ホームへ 自転車紹介へ プロフィールへ リンクへ